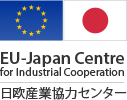ヴルカヌス・イン・ヨーロッパプログラム |
「理想と現実の狭間で」
| 細野 美晴 |
| ヴルカヌス・イン・ヨーロッパ2007年度派遣 |
| 語学研修:ラトビア語(ラトビア) 企業研修:a/s Latvijas Finieris社(ラトビア) 応募当時 工学部建築学科 在籍 |
私はヴルカヌスプログラムの存在を知ったときに、ラトビアという未知の小国に住む機会が与えられることは2度とないと思い、ラトビアにある a/s Latvijas Finieris社 を迷うことなく第一志望に選びました。派遣先がラトビアと決まった当初、親は『どこに行くんだっけ?ラザニアじゃなくて・・・何だっけ?』といった調子で、祖母は『暖かい国にいけるなんてうらやましい。』と言っていたのをよく覚えています。
ラトビアは、エストニア、リトアニア、ロシア、ベラルーシに国境を接し、バルト海に面している人口およそ220万人の国でそのうちの70万人が首都であるリガに暮らしています。公用語はラトビア語ですが、ロシア語しか話さない国民が多く、首都のリガにいたっては40%以上がロシア系ラトビア人です。したがって映画館ではラトビア語とロシア語の2ヶ国語が字幕として使われていたり、新聞も両言語で発行されています。また長いこと複数の国に支配された過去があり、今でもラトビア各地で占領されていた当時を思い起こすことができる建物や記念碑が見られます。私は語学研修と企業研修両方がリガでしたので、今のラトビアの経済状況からは想像できない空前のバブルで沸いていたリガで一年間過ごしました。
―語学研修―
多くのヨーロッパ諸国とは異なり大手の語学学校がないため、語学研修はプライベートレッスンでした。毎日、先生との1対1の授業でしたので新しい友達を作る機会が他のヴルカヌス生のようにありませんでしたが、自分のペースでラトビア語を学ぶことができました。また、自分が興味あるトピックについての文章を多く読むことができたりもしたので、ラトビアの歴史や文化について多くのことを学ぶことができました。授業以外でも、この期間は自分のための時間が多くあったので、隣国であるエストニアやリトアニアに行くことにより3国の関係や、それぞれの国の相違について肌で感じることができました。またラトビアのリガ以外の都市にも時間がある限り足を運ぶようにもしました。今では笑い話ですが、デンマーク旅行の帰りに、ラトビア第2の都市リエパヤへ帰国したら、空港で初めての日本人だったのか、入国ビザが必要かわからなかった入国審査官に入国を拒否されそうになった経験もしました。
語学研修中は、リガの中心部で一人暮らしをしている女性のアパートで暮らしました。よく想像されるいわゆるホームステイとは違いましたが、部屋を貸してくれたディアナとは、年齢も近く、ディアナ自身イギリスやアメリカに暮らしていた経験があるため、世界情勢を始め、ラトビアや日本の政治、経済、歴史などについてよく話しました。毎晩白ワインを一緒に飲みながら生活していたら、当然互いに仲良くなるのかもしれませんが、ディアナには語学研修中一緒に暮らした期間のみならず、一年間を通していろんな面でもお世話になりました。

ラトビアの短い夏の楽しみ
―企業研修―
私のインターンシップ先企業は、ラトビアの大手合板製造会社の a/s Latvijas Finieris でした。語学学校での1対1という小さなコミュニティーから、ようやくいろんな人と知り合う機会が持てる大きなコミュニティーの一員になれると思い、インターンシップを楽しみにしていました。
私の会社でのインターンの内容は、5月の企業訪問で前半4ヶ月間は会社の製造工程や品質管理について学ぶために工場内のラボで働き、後半4ヶ月間は家具を中心に製造している工場で家具デザインに携わる仕事をするということで、スーパーバイザーとスケジュールを決めました。また日本からの来客があった場合の通訳をするようにといわれました。しかし、実際企業研修が始まってみると、合板を作る際に必要な化学物質に対して私自身がアレルギーを持っていて、工場には近づかないようにとの医者の診断書が書かれてしまい、工場に立ち入ることができなくなり、結果的にラボでは数週間しか働けず、また家具を製造している工場は異動の数週間前に閉鎖されることが決定し、研修生は受け入れられないことになってしまいました。困難を乗り越えることによって人は成長をすると思ってヴルカヌスプログラムに参加していたので、多少の困難が待ち受けていることを歓迎でしたが、このような結果が待っているとは思ってもいませんでした。全く予定をしていなかった事態によって急遽やることがない状況が非常に長いこと続き、企業研修が始まる前に抱いていた目標は意味のないものと一瞬にして変わりました。4ヶ月近く『何をするためにラトビアに来たのだろうか』、『会社が払っているお金は何て無意味なものだろう』などといった考えが付きまといながら、時々回ってくる雑務をこなしたりしながら時は過ぎていきました。
冬休みに入る直前になり、ようやく2月から a/s Latvijas Finieris の子会社で木馬をはじめとした合板製品を製造している会社 Sia Troja で研修できることが決まりました。実施6週間でしたが、素晴らしい同僚に囲まれて一番インターンシップとして充実していた期間でした。

Trojaの同僚と
―まとめ―
この一年を通して自分が著しく成長したと胸を張って言えるかと聞かれたら、私は正直言えません。このようなプログラムにおいて、よく自分から行動を起こすことが大切だとか、センターがついているから安心だとか言われると思いますが、自分やスーパーバイザー、センターにも変えられない現実はあります。どんなに訴えてもある日突然受け入れてくれる別な部署が見つかるとは限りませんし、どんなに願ってもアレルギーはなくなりません。自らが行動を起こした結果、何かが実り自分が成長できたら確かにそれは素晴らしいことですし、理想的でもあります。残念ながら私はそのような体験談を書けるような体験はできませんでしたが、どんな状況においても前向きでい続けることが大切であるということは胸を張って言えます。やることがなかった数ヶ月間ラトビア語を磨いたり、日本の木材産業や日本工業規格について調べたりしていたことが最後に勤務した Troja で非常に役立ちました。どんな状況をも前向きに捉え、努力をする姿勢は忘れないでいることによって得られることは必ずあります。
今、ラトビアでの経験を振り返ってみても、ここには書ききれないほどさまざまなことがあった一年でした。不動産バブルの中での家探し、病院通い、家の水道パイプが故障し家中が水浸しになったこともありました。終わってしまえばあっという間ですが、一年という期間は決して短い期間ではありません。うまくいかないこともあります。もしかしたらうまくいかないことばかりかもしれません。ただ何事も足を踏み入れてみないと結果はわかりません。逆に予想もしていなかったことが学べるチャンスがたくさん転がっているかもしません。例えば、それまであまり意識することがなかった『占領国だった日本』ということについて考えられるようになったり、暖炉を使って真冬に部屋を暖める方法、林業、日本の木馬市場についても学ぶことができました。
一年間で想像をしていなかったことがたくさん起こり、そのときは一つ一つのことと向き合うので精一杯でしたが、多くの人の支えがあってこその自分であるということを改めて痛感することができましたし、そう思えるのは素晴らしい人たちとの出会いが詰まった一年だったからだと思います。

9月から始めた大学でのラトビア語講座のクラス
(2009年 執筆)
★ 体験談一覧へ