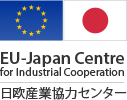ヴルカヌス・イン・ヨーロッパプログラム |
2007年フランス滞在記
| 鈴木 麻記子 |
| ヴルカヌス・イン・ヨーロッパ2007年度参加 |
| 語学研修:フランス語 (フランス) 企業研修:Renault社(フランス) 応募当時 早稲田大学理工学部機械工学科 在籍 |
2007年4月から3カ月半、フランス中部の街・アンボワーズにある語学学校に通ったあと、8月から翌年の3月まで、ヴェルサイユ郊外にあるルノーのテクノセンターで企業研修を行いました。当時の私は、海外に1ヶ月以上滞在した経験はなく、フランス語を学習したこともありませんでした。2007年4月7日の夕方、ブリュッセルからパリを経由してアンボワーズに到着。ホストマザーと笑顔で挨拶をして、ルノー社製の自家用車に乗り込みました。車内ではホストマザーが、犬を指差して「chien」と言い、車を指差して「voiture」と言いました。私は「しゃん」「ぼわちゅ」と聞いたまま発音を真似てみました。しかし何度発音を真似ても、ホストマザーの発音とは全然違っていました。こうして前途多難な留学生活がスタートしました。
さて、私がヴルカヌスに応募したのが2006年秋。まずはじめに、なぜヴルカヌスを選んだのかをお話ししたいと思います。
なぜ、ヴルカヌス?
「とにかく学生時代にしかできないような面白い経験をしたい」と思い、ヴルカヌスに応募しました。「ヴルカヌスに参加すれば、今まで自分が出会うことのなかったような、国籍も職業も異なる人たちに沢山出会える」「奨学金ももらえる」「ヨーロッパに一年滞在できれば、沢山旅行もできる」「海外企業でインターンを経験したという話題ができる」…などなど。こんなにもいいこと尽くめの留学プログラムを、他に見つけることはできませんでした。
なんでフランス? なんでルノー?
ヴルカヌスに応募した時点では、英語圏の企業を希望していました。しかし私は、企業の“求める人材像”に合わず、私が第一に希望する英語圏の企業とはマッチングが上手くいきませんでした。そして、他に希望する企業を選ばなければならず、“英語圏”という軸に拘るか、“自分が興味のある企業”という軸に拘るかでとても悩みました。最終的には、「人生は一度きりだし、まったく新しいことに挑戦してみるのもいいだろう」と思い、“英語”という軸に拘らずに、企業を選び直すことにしました。当時、ルノー会長兼CEOで日産CEOでもあるカルロス・ゴーン氏の著書「経営を語る」を読み、フランスと日本という距離的にも文化的にも遠い国にある巨大企業間で、Win-Winの関係を構築したルノーと日産に興味を持ちました。また、同族経営のミシュランでNo.2になるより、ルノーでの新たなチャレンジを選択したゴーン氏が率いるルノーなら何か面白いことが学べそうだと思い、ルノーを志望することにしました。
さて少し話が戻りますが、企業とのマッチングが上手くいかなかった理由は、「客観的に物事を捉え、相手がどのような情報を欲しがっているのか、自分がどのような情報を与えるべきなのかを常に考えること」が出来なかったからでした。これが、日欧産業協力センターを通さない留学プログラムであったら、この私の欠点を指摘してくれる人は誰もいなかったでしょう。留学先と自分との間に入り、アドバイザーとして意見や手助けをしてくれる日欧産業協力センターの存在は大変に有難いものです。
それでは、私が滞在していたアンボワーズや語学学校やホームステイについて、簡単に説明をしたいと思います。
アンボワーズ(Amboise)
パリから2時間ほど電車で南西に向かうと、ロワール川沿いに人口1.3万人ほどのアンボワーズという街があります。この街には、世界遺産に登録されているアンボワーズ城や、アンボワーズ城と地下道で繋がっていてレオナルド・ダ・ヴィンチが晩年を過ごしたとされるクロ・リュセがあります。定年でリタイアした年配の住民が多く、街全体でゆっくりと時間が流れている印象を受けました。
語学学校
語学研修を開始した時には、私を含むヴルカヌスのメンバー全員が、一番下のクラスに配属されました。私は、数も数えられず、挨拶や自己紹介も満足にできない状態でした。1週間経っても2週間経っても一向にフランス語が上達しない自分に大変な焦りや辛苦を感じたのを、今でも覚えています。一番下のクラスには、常時10人弱の生徒がいましたが、ほぼいつも9割近くの学生が日本人でした。
4月5月と、外を出歩く時も家でホストファミリーとごはんを食べる時も、片時も辞書と筆記用具を手放せませんでした。こんな私でも、「8月から企業研修が始まるので、それまでに出来る限り語学を習得しなければ」という精神状態に追い込まれていたので、7月中旬の語学研修を修了する時には、中級クラスの授業内容がほとんど理解できるようになっていました。中級クラスの半数ほどは、ヨーロッパ圏からの生徒でした。
ホームステイ
ホームステイ先は、初老のホストファザーとホストマザーの2人家族でした。私はフランス語を全く勉強せずに、フランスに行ってしまいました。その為、ホストファミリーの言うことが全く理解できず、彼らには沢山迷惑を掛けました。しかし彼らは、こんな私をとても可愛がってくれました。彼らの優しさを知り、後悔したことが1つあります。それは、ある程度フランス語を学んでから日本を発つべきだったということです。「日本にいる間にフランス語を勉強しても、なかなか頭に入ってこないし効率も悪いから、日本でフランス語を勉強する必要はない」という意見も勿論あります。しかし、ホームステイをする(=他人のお世話になる)と予め分かっているのだから、ある程度フランス語の基礎知識を習得してから日本を発つべきだったと思いました。
ホームステイを開始した時、私以外にドイツ人の高校生が既にホームステイをしていました。私がアンボワーズに滞在していた3ヵ月半の間に、アメリカ人の高校生2人・ドイツ人の高校生4人の計6人の生徒と居住を共にしました。6人の中で最も強く印象に残っているのが、ドイツ人高校生の女の子・ユリアです。ユリアは、英語もフランス語も流暢に話し、フランス語を全く話せない私をいつも助けてくれました。ユリアとの別れの日、彼女はびっしりと文字が書かれた小さな手紙と、アメがたくさん入ったビニール袋をくれました。「グリーンは、勉強がはかどらない時に、オレンジは元気が出ない時に、黄色は好きな人ができた時に舐めてね。だから黄色は少ないのよ」と笑っていって、手紙とビニール袋をくれました。その手紙の半分に、「信じる人には効く薬」と題打って、アメの効用に関する説明が書かれていました。こんな可愛くて愛情溢れるプレゼントをくれたことに、私はすごく感動したし、国籍を越えて心から信頼できる友人ができたことがとても嬉しかったです。
7月下旬、温かい田舎町を出て、ヴェルサイユ郊外へと居を移しました。8ヶ月間、主にどんな研修をしていたかについてお話したいと思います。仕事内容は、まさに22者22様(私たちの代は22人が派遣)でした。
研修内容概要
私は、ガソリンエンジンに組み込まれる2種類のセンサの新しい仕様書の作成や、品質チェックのための試験条件の決定などを主に行いました。研修期間中には、ルクセンブルクにある部品メーカーとの新プロジェクト立ち上げの件で同行し、特別に工場見学をさせてもらったりしました。また仕様書の作成や試験条件の決定といった仕事の傍ら、日本企業とのTVミーティングやface to faceミーティングのセッティングを行い、議事録を取ったりしました。また、ルノーと日産のセンサの仕様の違いを説明する為に、上司の代わりに会議に出ることもありました。
研修中の壁
研修中、最も問題となったのが、「語学力の低さ」です。仕事では、技術的な単語が多く使われるため、語学学校で習った日常会話用の単語は、ほとんど役に立たず、企業研修を開始した時には、上司や同僚の言っていることが全く理解できませんでした。すると上司や同僚が、私に対して英語で話してしまうのです。しかし、「ルノーでの研修目的の1つが、フランス語を習得することなのだ」と同僚に伝えてからは、常にフランス語でコミュニケーションをとってもらえるようになりました。
もう1つ問題となったのが、「日本人の当たり前が、フランス人にとっての当たり前ではない」ということです。私は上司に指示されて、日産の日本人エンジニアに連絡しなければならないことが何度かありました。日本人の常識からすれば、一研修生に過ぎない見ず知らずの学生が突然連絡をよこせば、他の仕事で忙しい相手がまともに取り合ってくれないであろうと容易に想像できると思います。日本のとりわけ大手メーカーでは、研修生はお客さんという認識が一般的だと思います。しかし、上司にこのことを説明しても、上司は全く理解してくれませんでした。それは、大学を修了するのに長期間の企業研修が必須であり、常時数多くの研修生が働いているのが当たり前なフランスで仕事をしている上司は、研修生も立派な戦力という認識を持っていたからでした。何度か上司と議論をして、最終的には、私が作成したメールを上司に転送し、上司が相手方にメールを送るという方法で、うまく連絡を取り合うことが出来ました。
企業研修中に学んだこと
まず、人に頼る大切さを学びました。「上司と上手くコミュニケーションが取れない」など、同期の仲間も自分と同じような悩みを抱えていました。そこで、他の人はどうやってその問題に対処しているのか、悩みだけでなく、その悩みに対する解決策などの情報共有をしました。これにより、自分一人では思いつかないような解決策を知ることができ、仲間に頼ることの大切さを痛感しました。
また、自分が得た情報を十二分に有効活用するよう努めました。日欧産業協力センターを通じて、過去のヴルカヌス参加者と連絡をとることができました。そして、企業における語学研修制度や住居手配の審査基準、社内の研修生向けプログラムの有無など、ここ何年間かで研修生を取り巻く環境が随分と変わってしまったことがわかりました。つまり、当時可能だったことが、現在は不可能だったり、またその逆もありました。では、今とは異なる当時の状況に関する情報が、全く無意味かというとそうではありません。「5年前はこんな前例がありました。確かに今とは状況が変わっていますが…」というように、前例として切り札にすることができるし、「5年前はこんなことができたなら、今それが出来ない原因は何だろうか」「誰かがこうしたなら、こんなアプローチがとれるんじゃないか」というように、前例を基に自分なりに思考することができます。ヴルカヌスを通じて、「自分が得た情報を、どうやって応用することができるか」常に考えるようになりました。
また、一口にエンジニアといっても色々なキャリアを知ることができました。現地の取締役に抜擢されたばかりの女性エンジニアや、ルノーに数年単位で出向する日産社員の方々、日産から海外企業への出向を何度も経験している管理職クラスの日本のエンジニア、日本を離れてフランスで活躍する日本人女性エンジニアなど。ルノーでの日本人研修生という少し特殊な立場を利用して、普段はコンタクトがとれないような方々から、積極的に話を聞くことで、様々な刺激を受けることができました。
ホストファミリーや語学学校の仲間と |
ルノーの同僚と |
帰国後
ヴルカヌスの経験を通じて、今までとは違った全く新しい環境に自分を置くことに対する恐怖感がなくなり、その代わりむしろ、全く新しい環境に自分を置くことは辛いけど楽しいのだと分かりました。この想いが今の私の軸になっており、今の私は新しい環境を積極的に受け入れるようになりました。以下に、留学後の2つの出来事を述べたいと思います。
1つめは、半年間のベルギー留学。2009年秋から、大学の交換留学制度を利用して、半年間ベルギーに留学する予定です。フランスの隣国であるベルギーで語学に磨きをかけると共に、1年間のフランス滞在で訪れることの出来なかった国々を訪れたり、日本とは違う大学のシステムや雰囲気に触れたいと思っています。ヴルカヌスの経験がなければ、フランス語圏の大学機関に留学するための土台はできていなかったでしょう。
2つめは、就職活動。最終的には、大学院の専門分野に直結したエンジニア職ではなく、全く未知の分野であるコンサルタント職を選択するに至りました。これは、ヴルカヌスの経験を通じて、私にとっては、“何をするか(仕事内容)”より“誰とするか(職場環境)”が重要であることを知ったからでもあります。一人が出来ることなんてごく小規模で、一人が社会に与えられるインパクトはすごく小さなものです。だから、何かスケールの大きいことをしたい時・社会に大きなインパクトを与えるようなことをしたい時には、仲間の存在がとても大事になります。そして私は就職先を選ぶ際に、自分の興味のある医療福祉工学から完全に離れない程度で、まず業界を選定したのち、経営理念や企業の雰囲気を重視して企業を選びました。ヴルカヌスの経験がなければ、このように就職先を選定することは出来なかったでしょう。
ヴルカヌスへの参加を考えている方へ
私にとってはこのヴルカヌスプログラムが、“いいこと尽くめ”の留学プログラムであったことは間違いありません。しかし、ヴルカヌスへの参加を考えているみなさんには、なぜヴルカヌスを選んだかを自分なりに考えて欲しいと思います。なぜならこの思考過程で、自分が留学に参加する目的がよりはっきりしてくると思うからです。自分が研修中に悩んだり落ち込んだりした時、「なぜこのプログラムに参加したのか。なぜルノーを選んだのか」これらのことをしっかりと考えていないと、自分が次にどんな行動をとらなければならないかが、全く分からなくなってしまいます。「自動車業界に興味があって、フランスで働きたい」のなら、目の前のことに一生懸命になる必要があるし、「将来自分がやりたいことの1つの土台になる」のなら、将来自分がやりたいことへのリサーチもしなければならない。ヴルカヌスが提供してくれる素晴らしい環境を、自分なりに十二分に活用して欲しいと思います。
ちなみに欧州では、高い能力と本人の意思があれば、それに見合った場や次への飛躍の機会を与えられます。実際に私たちの代では、研修先に就職する学生が3人もいました。
最後に
私がこのプログラムを修了するにあたり、様々な方のご支援がありました。精神的経済的に支えてくれた家族、留学に賛同してくれた教授、選考時から現在に至るまでお世話になっている日欧産業協力センターの方々、受け入れ先企業の上司や同僚、その他にも数多くの方のご支援がありました。
ヴルカヌスに参加して、「自分を助けてくれる仲間の存在はとても大事」ということを痛感しました。助けてくれるというのは、「辛い時に自分を支えてくれる・動けなくなった時に背中を押してくれる」というのと、「“仲間が頑張っているから、自分も負けまいと頑張ろう”って、今までの限界以上の力を出せる」という2通りの意味があります。そしてこの両方を満たしてくれる仲間が最強な存在で、“目の前の目標は違っても、突き詰めていくと同じような目標をもっていて、同じような困難を頑張って乗り越えている仲間”が、その最強な存在なのだと思います。今後も、こういう仲間に沢山出会って、沢山助けてもらって、沢山成長しなきゃと思います。その出会いや絆を広げたり強めたり出来るよう、これからも頑張っていきたいと思います。

最強!の仲間たちと
(2009年 執筆)
★ 体験談一覧へ