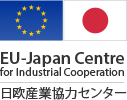| ヴルカヌス・イン・ヨーロッパプログラム 日本人学生対象 | |
| 三枝 洸介 |
| ヴルカヌス・イン・ヨーロッパ2018年度派遣 |
| 語学研修:英語 (ボーンマス, イギリス) 企業研修:Siemens Industry Software NV (ルーヴェン, ベルギー) |
| 現在の所属先:メドメイン株式会社 |
| 私は2018年度に開催されたヴルカヌス・イン・ヨーロッパプログラムに参加し、イギリスでの語学研修とベルギーでの企業研修を行いました。応募当時は、九州大学工学部で機械工学を専攻する学部4年生で、同大学院に入学した直後に休学をしてプログラムに参加しました。以前にも2ヶ月前後の短期留学の経験は複数回ありましたが、長期的に海外生活を経験することや、自身の専門分野を活かして研究業務に従事することに興味があったため、大変魅力的な機会だと感じ、プログラムへの応募・参加を決めました。 |
| 語学研修では、イギリスのボーンマス (Bournemouth) という町で約4ヶ月間、語学学校に通いました。様々なバックグラウンドをもつ、出身国、年齢、仕事、英語を学ぶ目的などが異なるメンバーが多く集まる語学学校でした。学校に通う期間もそれぞれ異なっていたので、クラスに新しいメンバーを迎えては送り出すという毎日で、SNSなどで今でも交流を続けている各国の友人たちと出会うきっかけにもなりました。ボーンマスは比較的温暖な気候や10km以上も続く美しいビーチで有名な一種のリゾート地で、週末や放課後にはビーチや近くのパブで友人たちと交流を深める機会にも恵まれました。語学学校での授業は、基本的な英文法の習得、実践的なコミュニケーションのトレーニング、学術的な読み物を題材にしたディスカッションの練習、イギリスの文化やイギリスに特有な英語表現の学習など、基礎から応用まで多岐に渡り、放課後のホストファミリーとの交流も含めて、適切な負荷を感じながら自身の語学力を鍛えることに役立ちました。 |
 語学研修地であるボーンマスのビーチ |
| その後、ベルギーのルーヴェン (Leuven) という町に移動して、Siemensでの企業研修を開始しました。Siemensは工学分野における様々な領域の製品開発に関わっており、私は自動車部門の振動制御・振動解析の分野の研究に従事しました。具体的には、機械振動の解析手法の一つとして知られる伝達経路解析 (Transfer Path Analysis: TPA) に関するもので、深層学習・ニューラルネットワークを用いた新たな解析手法の開発というテーマです。渡航前、大学では機械振動学を専門としており、趣味で人工知能や深層学習のアルゴリズムの活用についても学習していたため、まさに自分にとってぴったりのテーマで、会社には深層学習・ニューラルネットワークに関する知識や経験をもつメンバーがいなかったため自分自身で研究を主導していく必要があり、終始モチベーションを高く維持して取り組むことができました。研究チームのメンバーはヨーロッパやアジアの様々な国からの出身者で構成されており、現地のベルギー出身者が一人もいないほどで、そのような環境でコミュニケーションを取りながら業務を遂行していく際にはイギリスで学んだ英語力が活かされ、グローバルなコミュニケーションツールという側面での英語の面白さに気づくきっかけにもなりました。研究の成果や進捗が思うように出ない時期もありましたが、上司である振動制御・振動解析の分野のエキスパートに相談しながら、帰宅後も自室で関連する論文や参考書籍を読むなどして研究を進め、最終的には自身で論文を執筆し、ICEDyn 2019という国際学会に投稿することもできました。そのような機会を与えくれたプログラムや会社の上司などの関係者には大変感謝しています。 |
 企業研修地であるルーヴェンの広場 |
| イギリスやベルギーでの慣れない土地での生活や、企業研修での日々の研究業務には苦労することもありましたが、同じプログラムに参加するヴルカヌス生の友人や上司に相談するなどして、時には息抜きもしながら、目の前の課題をひとつひとつ乗り越えていくことでしか前には進めないということを学びました。ヨーロッパでの生活を1年間経験することで、より海外やヨーロッパを身近な存在として、さらには将来的な生活や仕事の場の現実的な選択肢として捉えられるようになったことも、プログラムを通じて得た大きな学びのひとつです。また、週末や休暇を利用してEU圏内の様々な国や都市を訪れ、各国の文化や雰囲気を実際に感じながら、現地の美しいものを見たり、美味しいものを食べたりしたことはいま思い返しても大変貴重な経験です。 |
 ブリュッセルのグランプラスの夜景 |
| プログラム終了後、帰国してからは、渡航前から創業に関わっていた、医療ITの分野でソフトウェアを開発する会社(メドメイン株式会社)で本格的に働き始めました。人工知能や深層学習の技術を活用した画像認識・診断支援技術の機能を有するソフトウェアの開発・販売を行うスタートアップ企業です。 |
| 上述のようなSiemensでの企業研修の経験を通じて、学術研究に従事することの面白さを感じるようになっていたため多少の葛藤はありましたが、プログラム参加前に休学していた大学院は後に退学し、いまはその小さなスタートアップ企業での業務に取り組んでいます。国籍を問わずに採用が行われているため、日本に拠点を置く企業でありながら、イギリスや中国に住むメンバーや日本に住む外国籍のメンバーなど、開発チームは海外の出身者が過半数を占めるような状況で、必然的に社内のコミュニケーションでは英語が用いられ、ベルギーでの企業研修を思い出すようなチーム構成や働き方となっています。新型コロナウイルス感染症の流行前には、アジアの各国の取引先への販売・営業活動や、その他の様々な国々の大学・研究施設との共同研究等のコラボレーションの目的で、海外との接点を持つ機会も多く、そのような場面でもプログラムを通じた海外経験が活かされているように思われます。また、創立して間もないスタートアップ企業の中で、日々のプロジェクトの推進のために、周囲の多様なメンバーと協調しながら、時には自分自身で大きな裁量権やリーダシップを発揮して、時には自分以外のメンバーの専門性や得意分野の力を借りながら、粘り強く目の前の課題に取り組んでいく姿勢は、やや抽象的ではありますがプログラムを通じて培ったものでもあります。 |
| さらに、語学研修や企業研修で直接的に学んだことではありませんが、同年度にプログラムに参加したヴルカヌスの同窓生との繋がりも、いまの私にとって非常に重要です。研修国や研修企業が異なるメンバーも含めて、同様の目的意識をもってプログラムへの参加を決断し、それぞれ異国の地で同様に新しい経験をし、逆にそれぞれに特有な経験もした友人たちは、直接的に長い時間を共にした訳ではなくとも、プログラム終了後も定期的に交流したり再会したりすることを続ける大切な存在です。帰国後もそれぞれがプログラムを通じて学んだことを活かしたり、新しい興味や目標を見つけたりして日々を過ごしています。そのような一生の付き合いにもなりそうな貴重な仲間を国内に得られたことも、プログラムに参加した大きな意義だったのだと、帰国後に振り返って感じます。 |
| 「ヴルカヌス (Vulcanus)」はラテン語で鍛冶屋の神様を意味しており、このヴルカヌス・イン・ヨーロッパプログラムは「鉄は熱いうちに打て」の格言に従って行われていると、プログラム概要に説明があります。この体験談の執筆時点(2020年7月)では、まだ帰国から2年ほどしか経過していませんが、大学の卒業・大学院への入学の直後という時期(熱いうち)に、このような貴重な経験ができたことを大変ありがたく思います。プログラムを通じて得られたかけがえのない経験や仲間を大切にしながら、日本とEU間の産業協力や経済発展にも貢献して恩返しできるよう、今後も自分という鉄を打ち、鍛えていきたいと思っています。 |
|
| (2020年 執筆) |
★ 体験談一覧へ