| ヴルカヌス・イン・ヨーロッパプログラム 日本人学生対象 | |
| 井手 亮我 | |
| ヴルカヌス・イン・ヨーロッパ2019年度派遣 | |
| 語学研修:イタリア語 (イタリア) 企業研修:Loccioni (イタリア) | |
| 私は2019年度ヴルカヌスインヨーロッパに参加し,イタリアで語学研修とインターンシップを行いました。私の専攻は機械系で、最近巷で話題のグローバル人材なるものに憧れてこのプログラムに応募しました。 | |
| 語学研修はマルケ州にあるRecanatiという人口2万人の田舎町で行いました。 | |
 Recanatiの街並み Recanatiの街並み | |
| 出発前にイタリア語をほとんど勉強していなかった私はあまりにも理解できないので面くらいましたが、田舎で英語も通じなかったため、人との交流に飢えてイタリア語の習得に励み1か月たつ頃には生活は困らなくなりました。A1という初心者レベルからB2という中級者レベルまで上がりました。朝は8時に起きて9時から13時まで20分の休憩を挟み授業が行われました。語学学校の生徒の8割以上は南米出身であり、彼らは自分たちの祖先の言語であるイタリア語を学びにきていました。私のようにイタリア語を使ってインターンや仕事をする予定がある生徒はほんの数人であり、一夏のバカンス気分で来ている生徒が大半でした。60歳以上の高齢者も多く、彼らはリタイア後の文化活動として夫婦や友達同士が来ていました。皆スペイン語やポルトガル語を母語とするため、飲み込みが非常に早く、既にイタリア語も話せるのではないかと思うほどでした。しかし、今思えば言語が近いからこそ初級レベルのクラスは勉強する人が少なかったです。現在スペイン語を勉強しているのですが、なんとなく文章が読め、相手の言っていることを聞き取れてしまうため、彼らの気持ちが理解できます。そんな中でも勉強を維持できたのはやはり同じような目的を持つ仲間の存在が大きかったです。毎月生徒が入れ替わるため、月初めにイタリア語を真剣に勉強してそうな学生を見つけ仲良くなり、一緒に勉強したり遊んだりしました。1ヶ月ずっと英語しか喋らない若者もいたので、自分の作戦は正しかったなと思います。 | |
| この語学研修期間にイタリア文化にどっぷり浸かりました。 | |
 行きつけのバール(喫茶店のようなもの) 行きつけのバール(喫茶店のようなもの) | |
| 朝はカプチーノを飲み、休み時間にはエスプレッソを飲み、夕方にはワインを飲む生活は非常に心地のよいものでした。町の人も生徒も皆喋るのが大好きで、ひたすら喋っていました。もちろんイタリア人にも性格の明るい・暗いはありますが、皆おしゃべりが大好きでした。帰国して数ヶ月たって感じるのはお店の人の態度の違いです。日本の店員さんは非常に丁寧で、言葉遣いにしても接し方にしてもレベルが高いなと感じます。しかし、同時に不自然であるとも感じます。あまりにも丁寧すぎて、そこまでかしこまらなくてもいいのにと日々感じます。イタリアも都会の方はもしかしたらそうなのかもしれませんが、少なくとも田舎では愛想の良し悪しはありますが、より人間らしかったなと思います。私も普段必要以上に丁寧になり過ぎないように気をつけるようになりました。 苦労した事として、イタリア語というその国でしか使われていないマイナー言語を学ぶ事へのモチベーション低下もありました。それもそのはず、私はグローバル人材なるものを目指していたからです。しかし、イタリア文化に触れるうちに彼らの事が好きになり、もっと勉強したいと思うようになりました。そして自分が目指したかったのはグローバル人材ではなく、互いの文化を知っているインターナショナル人材だと気づきました。 | |
| 企業研修は同じくマルケ州にあるLoccioni社で行いました。初日に全ての事業部を案内され、何がやりたいかを聞かれ、専攻とは違いましたが協働ロボットのプログラミングとシミュレーションを選びました。朝は8時半から12時半まで働き、1時間半の昼食休憩後2時から6時まで働きました。インターン生と雖も一人のエンジニアとして扱われました。たまにですが日本の会社との取引にも呼ばれ、同時翻訳のような作業もしてました。 インターン中は自分の意思を伝えるのに苦労しました。非常に働きやすい環境にあったものの、頭でわかっているのに言葉にならないもどかしさは辛かったです。最後まで話を聞いてくれる人が多かったので救われましたし、こっちがそっちの言語を話してるんだから余裕を持って聞いてくれよ!くらいの気持ちでいると丁度よかったです。 インターン期間中は会社の用意してくれたシェアハウスに他のインターン生と一緒に住んでました。Grande Fratello、英語で言うとビッグブラザーと呼ばれるアパートは社長の家の目と鼻の先にあり、1984という小説さながら常に監視されているのではないかと冗談をよく言っていました。シェアハウスにはイタリア人、中国人、ドイツ人など様々な国から来ており、共通言語は英語でした。一緒に生活するとお互いの食文化や、生活リズムや趣味の傾向などがわかり、数カ国ではありますがイタリア以外の文化にも触れることができました。 | |
| 私がいた会社は初代社長がまだ元気であり、現在は息子が2代目社長をしています。初代社長が死ぬと文化も少しずつ変わっていくので、初代社長が生きている会社をマッチングの時から希望していました。会社の文化は非常によく、エンジニアと作業員の仕事場が近いことや、月に1回社内プレゼンが開かれ別のオフィスの状況を把握したり、デスクが固定されていなかったりと働きやすい工夫が多かったです。出世したい社員はよく残業していましたが、たまった残業分は有給に回せるシステムでした。 その 文化に惹かれた社員が多いからか、皆精神的に余裕があり、休日や仕事終わりに遊びに誘い合う関係でした。同僚の出身の街を案内してもらったり、みんなでレストランに行ったりと仕事の時間と遊びの時間をどちらも楽しめました。彼らとは今でも連絡を取り合っています。 | |
 研修を受けていた会社 研修を受けていた会社 | |
| こういった会社の文化であったり、国の文化を理解するためにはやはり英語でなくてその土地の言語が必要不可欠だなとも感じました。その国の言葉を学ぶ過程で文化にも触れますが、それ以上に生活の中でこちらがイタリア語を喋っていると、気を良くして色々教えてくれたり、優しく接してくれました。英語でもコミュニケーションは取れますが、本当に相手を理解しようと思ったら相手の言語を学ぶことが遠回りに見えて近道です。 | |
| この1年間で身に着けた事は数多くありますが、上述したグローバル人材とインターナショナル人材の違いに気づけた事は自分の中で大きな喜びです。英語を話せない人が多く住んでいた地域で語学研修とインターンを行ったからこそ、彼らの文化を理解する面白さにも気づけました。みんなで共通の認識を持って英語で話すグローバル界隈で暮らすのもいいですが、異なる文化に染まりつつ、自分の文化を伝える役割はこのプログラムの醍醐味だと思います。アクセスが悪い田舎で英語も通じないよと友人に愚痴りながらも、その環境にワクワクしている自分もいました。この体験談をいつ読むかはわかりませんが、もしまだ行先を決める段階にあるなら田舎を薦めます。グローバル人材になりたい人は言うまでもありませんが、大都市がいいですよ。 | |
| 今後はインターナショナル人材になりたいと思い、日本とどこかの国、欲を言えばイタリアの間に立って仕事をしたいです。自分はどこででも生きていけるという自信がこの1年間でついたので、また新しい地域に行くのもいいかなと思っています。インターンをした会社から日本支社でのオファーを貰ったものの、開発現場がある場所で働きたい思いから断りました。この決断がどう転ぶかはわかりませんが、この経験が無駄になるものではありません。 | |
| (2020年 執筆) | |
| ★ 井手さんのビデオレターは こちら からどうぞ! (言語:イタリア語、英語字幕 & 和訳文掲載) | |
| ★ 体験談一覧へ | |
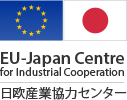
イタリア Loccioni 研修
Search
We use a selection of our own and third-party cookies on the pages of this website. If you choose "ACCEPT ALL", you consent to the use of all cookies. You can accept and reject individual cookie types.
