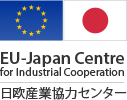
グリーン水素・大規模製造の展開について|日欧オンラインワークショップ
プログラム最新版はこちら (CLICK)

水素は、2050年には世界のエネルギー需要の4分の1を満たすと予測されています。
しかし、現在の水素生産の95%は化石燃料を使用しており、低炭素水素のコスト競争力はまだ低い状況です。
2050年にEUと日本が掲げるカーボンニュートラルを真に達成するためには、水素は再生可能な資源から製造されなければなりません。
再生可能水素は、特に蓄電、大型輸送、エネルギー集約型産業(再生可能電力で限界がある分野)において、脱炭素エネルギーを実現する可能性があります。
再生可能電力と再生可能水素が一緒になれば、統合された、柔軟で、かつクリーンなエネルギーシステムを実現するための相乗効果が得られます。
このビジョンを実現するためには、再生可能な水素を使った製品やプロセスの供給を大幅に増やすことが必要です。
そのためには、既存のバリューチェーンにおいて、化石由来の水素を再生可能な水素で代替し、技術の成熟度を高め、市場での実行可能性と競争力を高める必要があります。
こうした状況を踏まえ、本イベントでは、欧州と日本の専門家の方々にご登壇いただき、大規模なグリーン水素製造のための公共政策と展開に関する最新の動向を共有するとともに、日欧のグリーン水素プロジェクトにおける協力の可能性についても議論していただきます。
録画 & 講演資料
注釈: 経済産業省によるオープニング・プレゼンテーションは、講演者のご希望により録画から削除致しました。
講演資料を見る/ダウンロードする 要約日欧におけるグリーン水素政策の最新動向
欧州委員会と経済産業省のご登壇者様より、2050年のカーボン・ニュートラルという共通目標達成のために取り組んでいる公共政策の現状について、グリーン水素に焦点を当ててご紹介いただきました。
欧州委員会エネルギー総局のトゥドール・コンスタンティネスク主席顧問は、欧州グリーン・ディールは再生可能エネルギーへの更なる投資を促すものであり、2020年に発表された「欧州水素戦略」は水素エネルギーの普及とバリューチェーンの構築へ向けた具体的なステップが示されており、欧州の長期的な脱炭素化戦略においての水素エネルギーの重要性を示している、と述べました。そして今後克服すべき課題としては、運輸部門や家庭における水素の利用を促進し、徐々に天然ガスを代替していくことや、水素貯蔵能力を高める更なる研究開発があると述べたうえで、欧州クリーン水素アライアンスや日本等との国際連携が今後重要になってくると指摘しました。
水素は、エネルギー移行のミッシング・リンクから、エネルギーシステムの中核になる。
欧州委員会エネルギー総局 トゥドール・コンスタンティネスク氏
経済産業省の白井俊之水素戦略室長は、水素社会の実現へ向けた政府主導の様々な取り組みを紹介しました。2017年に採択された「水素基本戦略」以降、水素の発電と利用を促す上で重要な燃料電池の開発計画がいくつか発表されていると述べた上で、日本におけるモビリティ、発電、定置用燃料電池、地域連携地点(ハブ)、国際サプライチェーン等の様々な分野で現在進行中及び計画中のプロジェクトに触れました。多種多様なプロジェクトが動いている点や、2020年12月の「水素バリューチェーン推進協議会」設立から分かるように、産業界は意欲的に水素事業に取り組んでいると述べました。また、「グリーン成長戦略」の策定による政治的枠組みの確立や、「グリーンイノベーション基金」の造成による経済的支援など、水素関連政策の最新動向にも触れ、日本は、水素の普及に向けた利害関係者との協力関係を強固にするために、地方の取り組みを支援すると同時に国際的なハイレベルな対話を進めていくと述べました。
日欧における大規模な統合グリーン水素プロジェクト
このセッションでは、日欧双方の企業より、大規模な統合グリーン水素製造プロジェクトをいくつかご紹介いただきました。
基礎化学品の製造で欧州をリードするNobian社の新規事業マネージャー、ヨースト・サンドバーグ氏より、オランダで実施されている「DJEWELS」プロジェクトをご紹介いただきました。同プロジェクトは、旭化成の膜技術を用いてNobian社の施設でグリーン水素製造を拡大し、再生可能な電力から再生可能なメタンまでのバリューチェーン全体を産業規模でカバーしており、今後は1基あたり20MWの電力生産から1GW以上にスケールアップすることで、更なる低コスト化を目指しています。また、本プロジェクトはEUの支援を受けてオランダ北部で進めている大規模な水素エコシステム「水素バレー」に含まれている、と述べました。
繊維製品、化学品、電子関連材料メーカーである旭化成株式会社より、クリーンエネルギープロジェクト長の磯部康秀氏にご登壇いただき、アルカリ水電解システムを中心にご説明いただきました。同技術は、すでにドイツと日本のプロジェクトで採用されており、ドイツでは、CO2を再利用する技術を共同開発する研究開発プロジェクト「ALIGN CCUS」に、日本では、再生可能エネルギーから水素を製造する大型施設「福島水素エネルギー研究フィールド」に取り組んでいると述べていただきました。
スペインの天然ガス会社Enagas社の水素エネルギーコーディネーターであるマリア・ハエン・カパロス氏より、同社の子会社Enagas Renovable社の再生可能エネルギー(主にバイオメタンとグリーン水素)促進に向けた供給網の面での取り組みをご紹介いただきました。一つ目は、欧州から「欧州共通の関心事である重要なプロジェクト(IPCEI)」として認定されている水素の生産量と需要が多い地域を結ぶ「Green Crane」。二つ目は、マヨルカ島に水素エコシステムを構築する「Green Hysland」の実証実験。後者に関しては、他の地域でも転用可能な大規模な水素ハブの構築を目指しているとご説明いただきました。
日本の産業用化学製品をリードする東レ株式会社の主任研究員である出原大輔氏にご登壇いただき、水素社会を実現する上で同社が開発した様々な基幹素材をご紹介いただきました。同社は、電解槽によるグリーン水素製造は、電気・非電気の両分野の脱炭素化につながるため、カーボンニュートラルを実現するための重要な要素であると考えており、NEDOの山梨県における日本初のメガワット級PEM電解槽の共同開発プロジェクトに参画しています。また、2015年からは、ドイツの子会社が世界で最もコンパクトなメガワット級のPEM電解槽スタックを開発するなど、この分野で欧州でのプレゼンスを高めています。講演の最後に、出原氏はグリーン水素の製造コストについても言及ししていただき、第2セッション終了となりました。
水素プロジェクトの協力可能性
最後のセッションでは、グリーン水素における欧州と日本企業の共同事業についてパレリストが議論し、今後の更なる交流の道を探りました。
日本側としては、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)燃料電池・水素室長の大平英治氏より、日本のグリーン成長戦略における水素の重要性を述べていただきました。同戦略において、水素は特定された14の優先分野の一つであり、他のいくつかの分野でも言及されています。NEDOは現在、燃料電池応用の促進、水素エネルギー需要の拡大と既存エネルギーシステムへの統合に向けて注力していると述べました。そして課題としては、水素ステーションのコスト削減、生産規模拡大のためのタービンの高効率化、包括的なエネルギー管理システムの開発などを挙げました。課題解決に向けて製造技術の向上、大規模利用の前提となる国際基準の策定、モデル構築による経験の共有などが今後の協力分野として考えられる、と述べていただきました。
EU側としては、 燃料電池水素共同実施機構 (FCH-JU)のエグゼクティブ・ディレクター、バート・ビーブイック氏にご登壇いただき、水電解プロジェクトを2025年には100MW以上、2030年にはGW規模に拡大したいとの展望を示していただきました。また、欧州での日欧共同事業の一例として、鉄鋼・石油精製業での水素利用を促進する資金支援を行っていると述べました。日本が現在関与している同機構の事業としては、水素バレー利害関係者が情報共有出来るプラットフォーム「ミッション・イノベーション」、欧州共通の水素起源保証スキームの標準、フリー触媒に関する研究協力、水素充填共通プロトコルの整備を挙げ、NEDOとFCH-JUの参画も含めた、新たな協力分野を示唆しました。
「日本のグリーン水素がヨーロッパのグリーン水素であるように、すべての水素製造方法について世界的に合意し、CO2排出量についても合意することは非常に重要です。これは、今後の国際取引を可能にする重要なことです」
燃料電池水素共同実施機構 (FCH-JU) バート・ビーブイック氏
ハイドロジェン・ヨーロッパ事務局長、ジョルゴ・チャツィマルカキス氏より、オーストリアでの鉄鋼生産の脱炭素化に向けた社会実験、パリでの水素タクシーの大規模導入などをレ例として挙げ、日本と欧州の多様な企業提携による産業プロジェクト、研究プロジェクト、水素・燃料電池の導入プロジェクト等をご紹介いただきました。また、日本企業が欧州の水素市場に参入する際の主な課題として、プレゼンスの低さ、欧州特有な基準のクリア、中国及びアメリカ市場に比べて障壁が高いことを述べたうえで、欧州企業との提携によってこれらを克服できる可能性があると述べました。現在同団体が取り組んでいる事業の中で、水素のオークションシステムや、凧技術を使って船上で水素を生産する「Oceanenergy」プロジェクトをご紹介いただき、これらのプロジェクトにおいて日本企業と提携していきたいとの展望を述べていただきました。
最後に、ドイツのコンサルティング会社ECOS Consult社のシニア・プロジェクト・マネージャー、ヨハンナ・シリング氏にご登壇いただき、日本とEUがグリーン水素に関する国際的なプロジェクトを実施する際に、どのような分野で、どのような基準で、どのようなモデルからインスピレーションを得ることができるかについての洞察を述べていただきました。まず分野としては、多様な電気分解技術の向上及び国内外のサプライチェーンコスト最適化に着目できること、そして国際事業立ち上げの基準としては、利害、技術、資金調達方法の相補性が重要と述べたうえで、日本と欧州はそれぞれ異なる専門分野を持っており、それらを組み合わせることが出来ると述べました。そして現在、北九州において進んでいる大規模洋上風力発電プロジェクトについては水素製造も行われており、工業地帯や都市部が近いことから、共同グリーン水素プロジェクトを行う前提条件が整っていると述べました。
閉会の辞
閉会の辞として、欧州委員会と経済産業省のご登壇者様お二方にご登壇いただきました。グリーン水素に関する欧州と日本の二国間協力の重要性を改めて強調するとともに、日欧両国はそれぞれ異なる理由で水素を開発してきたが、カーボン・ニュートラルという共通の目標の下、新たな相乗効果を見出すことができると述べていただき、閉会となりました。
なお、グリーン水素に関するワークショップは計3回の開催を予定しております。今回のワークショップは初回でして、今後、輸送などの最終用途・国際取引に関する問題について焦点を当てたワークショップを2回開催する予定です。
